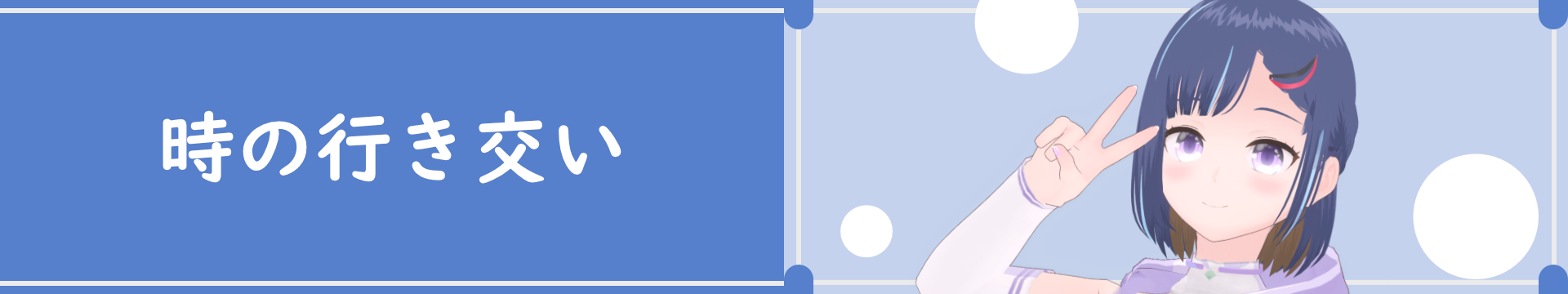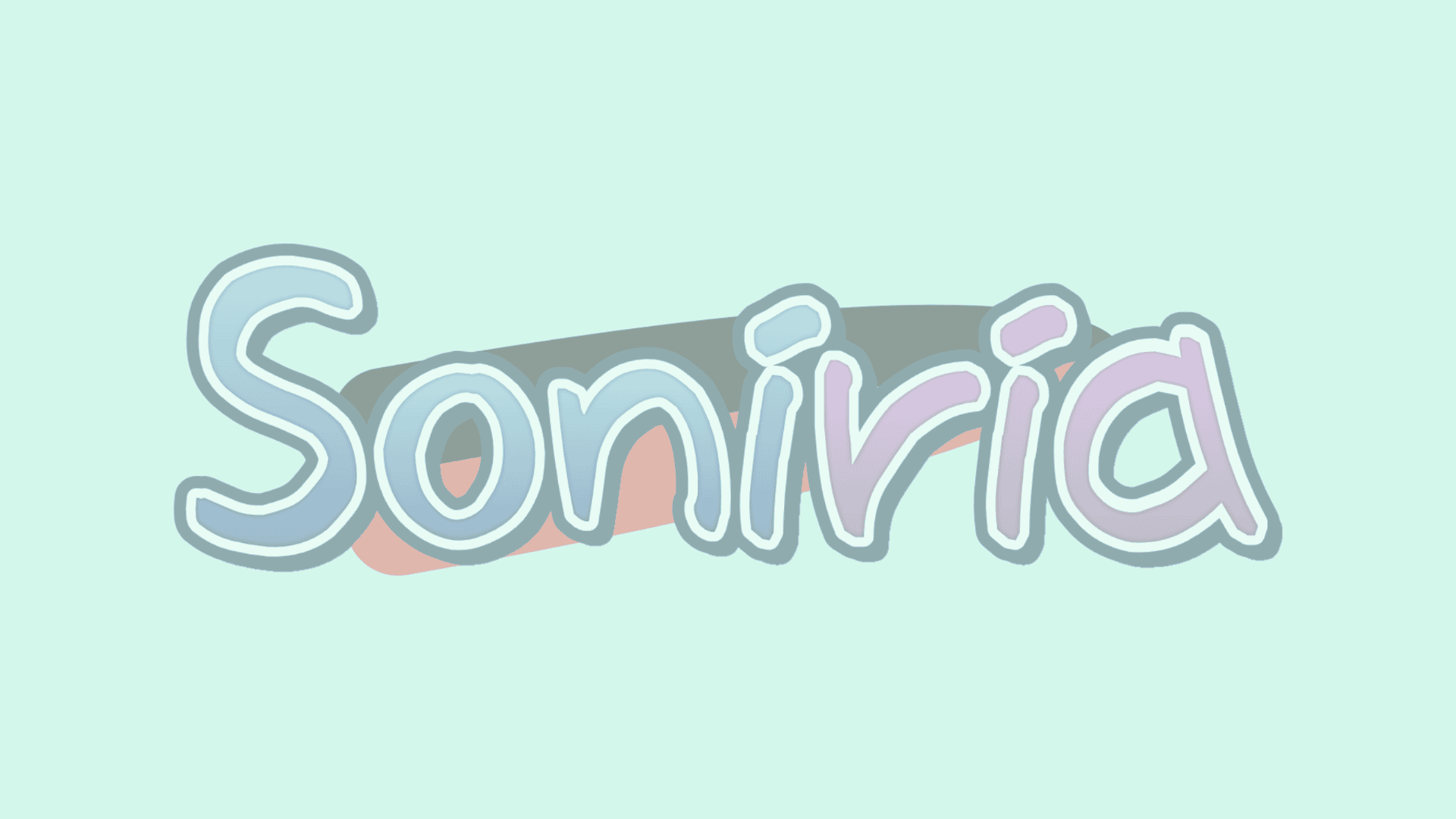目次
挑戦を通じて、可能性を探索する1年を過ごす
1.背景
4周年を迎え、自らの活動を『羅針盤の結晶体』として公開してから、数日が経ちました。ここ1ヶ月くらいは、自身の軌跡を確認して現在地を確かめるための、内省的な時間を過ごしていました。
これまで、どちらかというと先行する直観を頼り、後づけで論理を補強する流れでの活動を続けてきたはずなのに、振り返れば、その軌跡は一つの説明可能な像を描きだしているような印象を抱きました。
そして、私は一つの仮説に辿り着きました。
「この4年間の活動において、他ならぬ私自身が、自分の可能性を最も過小評価している領域があるのではないか」と。
これまでの状況の理由と、これからが期待できる根拠。その両方が、自分の中で確かなイメージとして浮かび上がってきた今、この仮説を検証する時が来たと感じています。
5年目となるこの一年は、果たして仮説としての「在るべき状態」へと船を進めていく余地はあるのか、初めての意識的で、戦略的な挑戦の年にします。この挑戦の行く末が、今後の活動で私が手にできる選択肢の幅を、変えることになるかと思います。これは、私の1つの大きな外海での検証になります。
2.5年目に向けて:KGIとKPI
この挑戦への客観的な目安として、以下の数字を割り出しました。
- KGI(最終目標): 5周年時点で、チャンネル登録者数 1,200名
- KPI(過程目標): 年間42本の動画の投稿 / 外部環境での年間34回の情報発信
正直に言えば、1,200名という数字自体に、特別な意味はありません。これは、後述する活動計画を積み上げた結果、到達しうるであろう一つの試算値です。4周年時点で登録者数37名の現在地からみても、おそらく、やや楽観に寄っていることは否めません。
この目標を達成するには、その過程で計画自体に「手を入れる」必要が出てくるでしょう。その課題に対して、どのように向き合い、何を得られるのか。そこにこそ、探真を愛好する者として、目指す真の意義があると感じています。
目下は、淡々とKPIに沿ってコンテンツ制作を実施するというシンプルな取り組み内容です。
(なお、初月はコンテンツ準備が発生するため、厳密な本数は変動することを補足します)
3.対象とする層と届けるもの
この一年で、私が活動を通じて接点を築きたい対象の層は、二つの異なる領域の方々です。
一つは、「思索を好み、物事の本質を探求するが、それを形にすることには手薄な層」。
もう一つは、「手を動かし、創造することを愛するが、その背景にある哲学を言語化するのは手薄な層」です。
日本の生産年齢人口7,400万人として、知的好奇心が高く、実践に課題を持つ「ある種の思想家層」を約148万人。国内のクリエイター人口約200万人として、言語化に課題を持つ「創作家層」を約56万人と推定しました。この合計のインターネット上の潜在的な対象に対し、1年間でアプローチします。
上述の合計76本のアプローチを通じて、潜在層の約0.06%に活動を発見してもらい、結果としての1,200名へと積み上がればと試算しています。
本来、交わることの少ないであろうこのそれぞれの層が、時の行き交いという「交差点」で出会い、互いの視点に触れることで生まれる、新たな「発見」や「気付き」。それこそが、私が届けたいと考える内容になります。
4.活動計画:3つのYouTubeシリーズ
この目標を達成するため、YouTubeを拠点とし、以下の3つの動画シリーズを軸に、これまでとは頻度を切り替えて、情報発信を試みます。
- 【A】弁証法で探る(月1本): 私の「思想」の核となるシリーズです。日常や創作における様々な気づきを、弁証法という思考で分解し、新たな視点を模索します。
- 【B】創作の欠片(月1.5本): 私の「実践」の紹介となるシリーズです。この4年間で蓄積したアバターやワールドといった創作物への取り組み経験を題材に、その細部へのこだわりや想いを、Shortsと通常動画で紹介します。
- 【C】長屋談義(月0.5本) / 作業会の便り(月1本): 私の「関係性」と「過程」を示すシリーズです。友人との創作の進捗会や、コミュニティ活動の記録を通じて、『時の行き交い』が描く空間の現在地を、Shortsと通常動画で紹介します。
これらの活動は、年間の動画投稿本数に換算すると42本、活動当初から堅持していた隔月1本ペースと比較し、8倍のペースとなります。生来、ON/OFFの波がある私にとって、定常的な活動は挑戦的な面も含みます。
ただ、昨年の総活動時間から見れば、この計画全体の月間作業負荷は、約1/3程度に収まる見込みです。仮に試算を上回ったとしても、そのリズムさえ掴めれば、決して不可能な配分ではないはずと見込んでいます。
なにより、各動画コンテンツは、2年分以上のネタとしての既存ストックがあるか、リアルタイムに補給できるか、いずれかの要件を満たしており、企画自体への負荷は削り落とせています。そのため、この一年は、私自身の「定常的な活動への心理的耐性」を確かめる、重要な検証期間でもあります。
しかし、拠点であるYouTubeでの発信を強化するだけでは、まだ見ぬ「群賢」との出会いには限りがあります。そこで、これと並行し、もう一つの探索を行います。
5.思想と実践の交差に向けた探索
活動を補強し、対象層のうち「非Vtuber視聴者層」の方々との新たな接点も見つけに行くため、外部プラットフォームも活用し、発展の可能性を探りつつ、外海へと航行していく計画です。
- note(月2本): 「思想と実践のパイプライン」の言語化を試みる、検証の場です。
『弁証法で探る』の背景にある思索の深掘り、創作物の細部へのこだわりに触れる記事、
それぞれ、投稿した動画に基づいて補足する形式で発信し、思想家のような思索を好む層との接点を目指します。 - Speaker Deck(2ヶ月に1本): 「思考プロセス」を可視化する、共有の場です。
主には過去に動画で用いた資料を再利用しつつ、これまでの軌跡を公開します。実践的な知見を求める層との接点を試みます。 - Behance(四半期に1回): 「創作する力とその過程」を一覧化する、展示の場です。
これまでの創作を中心にポートフォリオとしてまとめ、定期的に更新しつつ、関心を抱くアーティスト、クリエイター層へのアプローチを期待します。
目安として、これらを合わせて年間34回分の情報発信を見積もっています。
ちなみに上述の月間作業の負荷目安は、これらの内容も工数内に含めた試算となります。
普段とは異なるプラットフォームや手段であるため、当面は着実にペースを掴めることが目標になります。
6.この挑戦の先にあるもの
この計画の最大の目標は、数字の達成ではありません。それは、「一人でも、長屋の群賢と出会えること」です。
私の活動の本質は、数を追うことにはありません。一定の規模は、あくまでこの『時の行き交い』という空間をできるだけ主催者に一極集中させず、描く理想的な状態として動き出すような、必要であろう要素に近いものです。何よりも重要なのは、その関わる方々の「想い」であるかと考えています。
この一年間の挑戦の果てに、たとえ一人でも、背中を預けられるような賢者と出会うことができたなら、それは非常に意義のある時間を過ごせたものとして、6年目以降の未来に希望を持てるのではないかと感じています。
羅針盤の結晶体が示す、新たな航路へ。
私の5年目の挑戦を、どうか見届けていただけると嬉しいです。